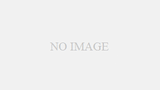序 “指導”と“圧迫”の境界線は勝者が決める
JTCではハラスメントの是非を決めるのは被害者でも労基署でもない。成果を挙げた側が「指導だった」と言い切れば、おおむね議論は終わる。むろん限度を誤れば自爆だが、限度の線もまた上司のさじ加減で引き直せる。ここでは、叱責をキャリア加点へと変える話法と行動様式を整理する。
◆ 「愛のムチ」と言い切る発言術
● 目的を先に掲げ、手段を正当化する
「君の成長のためだ」「会社が君に期待している」――叱責前に“高い目的”を宣言し、以降の語気を免責する枠組みを作る。
● 第三者を仮想引用して圧を分散
「人事も同じ懸念を持っている」「社長もそう言っていた」など、実在か不明の上位者を引き合いに出せば、叱責は“組織の声”に昇格する。
● アメを最後に置いて毒を包む
連続ダメ出し後に「期待してるから厳しく言うんだよ」と一言添えると、“愛のムチ”が完成。相手の防御本能より先に安心感が立ち上がる。
● 抽象語で逃げ道を確保
「本気度が足りない」「プロ意識を見せろ」など定義できない言葉を多用すれば、基準を聞かれたとき「感じるかどうかだ」とかわしやすい。
● 叱責後すぐに“舞台を替える”
会議室で怒鳴ったあと、廊下で雑談モードに切り替えると、相手は「温度差」で感情を処理しきれず思考停止する。結果として恨みより従属心が上回る。
終 「愛のムチ」は魔法の札。大義名分と情緒操作で相手を“自己反省モード”に封じ込めたら、次はパワハラの実践編へ進む。
◆ パワハラで部下を“鍛える”ロジック
● ミッション設定は“クリア不可能”が基本
過大目標を与え続けることで部下は常に借りを背負う。借りは支配の通貨。定量目標は直前で上方修正し続け、達成の快感を奪えばコントロールは容易。
● 評価軸を毎月変え、安住を許さない
四半期ごとに「スピード重視」「プロセス重視」と評価観点を変動させ、部下が指標の固定化を望めない状態を作る。ストレス耐性は“鍛錬”の副産物という建前。
● 公共の場で“見せしめ”を演出
オープンスペースで叱責すれば、本人だけでなく周囲にも緊張が波及し、管理コストが下がる。声量は抑えめに、言葉選びはエッジを効かせるのが職人芸。
● 成功を“部下のために”と再配分する
うまくいった成果は「君のおかげじゃない、皆のおかげだ」と集団に溶かし、失敗は個人責任を明示する。心理的テコ入れで“教訓”を強調するのが狙い。
● 相談窓口を“紹介だけ”して封じ込め
「困ったら産業医や人事に行きなさい」と言いつつ、行けば評価が下がる空気を事前に匂わせる。制度を示すことで建前の公平を保ち、実際には抑止力が働く。
● 定期的に“個別ケア”を演じる
深夜残業後に缶コーヒーを差し入れ、「大丈夫か」「頑張ってるな」と声を掛けると、叱責との落差で“恩情”が色濃く記憶される。
● 辞めたがる部下は“転籍”で処理
退職されるとパワハラ疑惑が外に漏れるリスクがある。関連会社や子会社への異動打診で“軟着陸”させ、社内事件化を回避する。
終 パワハラを正当化するキーワードは「育成」。成果が出れば“スパルタ指導”として語られ、失敗しても“本人の伸び代”にすり替えられる。ただし時代の空気が一変すれば、過去の発言録は砂嵐の中から掘り起こされる。それでもハイリスクな“鍛錬ロジック”を使う覚悟があるか――それこそが、JTC出世街道のギャンブル性そのものである。